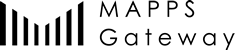利用者と目線を揃えて最短距離の動線を構築
提供機関 | 石川県金沢城調査研究所
URL | https://www.pref.ishikawa.jp/kncastle/d-nagaya/
構築方式 | オリジナルサイト・リンク
3つの切り口が「同居」するイメージを「長屋」で表現

江戸時代、金沢城には多くの「長屋」が存在しました。現存するのは1858年に再建された重要文化財・金沢城三十間長屋だけとのことですが、「金沢城デジタル長屋」のトップページを飾るイラストは見た目がそっくり。実際に三十間長屋をモチーフに書き起こされた作品とのことで、実際の扉は2つのところサイトの選択項目に合わせて3つに増量されたのだとか。
では、さっそく中に入ってみます。長屋の「みる」の扉を開くと、絵図・出土品・石垣・動画という4つのボタンが現れます。ここでは絵図を選んでみましょう。

次の画面で「金沢城」を選ぶと地図が掲載されている画面が表示され、左のボタンから見たい絵図を選択することができます。いずれかを選ぶと、絵図の一覧が表示されます。

ここからがI.B.MUSEUM SaaSのページとなります。キーワードの入力ボックスの下にある分類を見ると、「絵図>金沢城>全域図」と3階層目(項目によっては2階層目)までが選択されていることが分かります。プルダウンメニューで条件を指定する代わりに、直感的なボタンクリックで階層を降りてきたことになりますが、こうして見ると「たどりやすさ」が一目瞭然ですね。

ここでひとつを選ぶと、画像と詳しい解説が表示されます。もちろん画像は拡大できますので、特に絵図はじっくり見ることができます。


同様に、「よむ」では金沢城の解説や調査研究についてのPDFファイルなどが公開されています。「しらべる」は詳細検索の画面で、下の画像のように細かく分類を選ぶことができます。

改めて全体像を俯瞰すると、金沢城デジタル長屋はとてもシンプルな構成ながら、利用者目線のもと最短距離で目的の資料に辿り着けるように設計されていることが分かります。金沢城にまつわる多種多様な資料を検索できるデジタルアーカイブ。絵図、出土品からパンフレット、紀要まで、タイプの異なる資料があることを伝え、豊富さをアピールするためにも、トップには資料の種類からの検索方法を置きたくなりそうです。
ところが、ここで発信する側の目線に走らなかったのが金沢城デジタル長屋です。「みる」「よむ」「しらべる」という利用者の純粋な目的・行動で分類しているのは、「画面を開いた人はここで何をしたいのか」という利用者の目に視点を合わせる形で設計されたのではないでしょうか。デジタルアーカイブは、利用者あってのもの。この利用者視点の姿勢は、大いに参考にしたいものです。